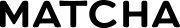【開催レポート】MラボRADIO #05「なぜ広域連携が必要なのか?単独では難しいインバウンド誘客を広域で協力する理由」
2025.02.20
Column

第5回目のテーマは「なぜ広域連携が必要なのか?単独では難しいインバウンド誘客を広域で協力する理由」。今回は、一般社団法人キタ・マネジメントの三好飛鳥さんをゲストに迎え、愛媛県南予エリアにおける広域連携の重要性とその具体的な取り組みについてお話を伺いました。
※MラボRADIOとは・・
インバウンドの最前線で活躍する方々が、訪日客の視点に立った実践的な施策や取り組みを語る、ラジオ感覚で楽しめるトーク番組です。「訪日客の心を動かす取り組みとは?」「地域に訪日客を呼び込むためにはどのような工夫が必要か?」といったテーマを掘り下げ、インバウンド施策に取り組んでいる皆様に新たな発想や具体的なヒントをお届けします。
■ 開催概要
開催日時: 2025年2月18日(火)13:00~14:00
登壇者:
スピーカー:
一般社団法人キタ・マネジメント 三好飛鳥
愛媛県大洲市出身。IT企業勤務を経てUターンし、大洲市の公式観光サイト「Visit Ozu」の広報を担当。MATCHAと協力し、愛媛県南予エリアの多言語メディア「Southern Escape Ehime(https://southern-ehime.mcmjp.com/jp)」にも携わる。広域的な情報発信やプロモーションに取り組み、地域の魅力を世界へ伝えている。
株式会社MATCHA プロデューサー 秋山
埼玉県出身。明治大学国際日本学部卒。日系旅行会社で訪日ツアーの企画・オペレーション、五輪事前キャンプ事務局運営に従事した後、2022年にMATCHAに入社。現在、プロデューサーとして自治体や企業のインバウンドプロモーション企画を担当。
■ 大洲市の取り組み
- 大洲市の位置: 愛媛県南予エリアに位置し、松山市から電車で約1時間半の距離にある。
- インバウンドに向けた古民家を再生したまちづくり
歴史ある町並みを活かし、古民家をリノベーションして宿泊施設や店舗として活用。特に「NIPPONIA HOTEL 大洲城下町」は、歴史的建築を再生した宿泊施設として高い評価を受けている。観光戦略として、明確にインバウンドをターゲットとした取り組みを進めている。そのため、海外の旅行会社との連携を強化し、現地視察やツアー造成のサポートも進めている。 - MATCHAとの協力: 愛媛県の事業であるトライアングルエヒメの一環により、1年半にわたりインバウンド向けの情報発信を継続。愛媛県南予エリアの多言語メディア「Southern Escape Ehime」を運営しながら、訪日客に向けた魅力発信を行っている。地元向けのインバウンドに関する勉強会なども共同開催。
■ トーク内容
1. 広域連携が必要な理由

大洲市単独でインバウンド誘客を進めようとしても、限界があるなと感じるのが現実です。松山空港からのアクセスが限られていることもあり、訪日客がわざわざ大洲を目的地にするのはハードルが高い。そうした中で、周辺の内子町、西予市、宇和島市と手を組むことで、それぞれの強みを活かし、地域全体としての魅力を高めることが実現できます。
三好さん曰く、「例えば大洲市には歴史的な街並みや文化があるけれど、それだけの魅力では長く滞在してもらうのが難しい。だからこそ、隣の町と一緒に“訪れる価値のあるエリア”として発信していくことが大事」とのこと。
広域での連携によって、訪日客がいくつもの町を巡る動線を作り、滞在時間や宿泊数の増加につなげていくことが期待されています。各地域が単独で戦うのではなく、互いに補い合いながら観光の魅力を発信していくことが、結果的に地域全体の活性化につながります。
2. インバウンド視点での情報発信と課題
観光コンテンツを発信する際には、具体的なペルソナを明確にすることが大事です。ターゲットとしている欧米豪の訪日客は長期滞在の傾向が強く、周遊を前提とした情報発信が有効になります。ただ「観光地の紹介」をするのではなく、彼らの興味や旅のスタイルに寄り添った発信が求められます。
三好さんは、実際に海外に訪れた際の経験を例に挙げました。「ロンドンのような都会でさえ、公共交通の仕組みが分かりにくかったんです。いつ電車が出発するかやチケットをどこで買うかなど迷うことや不安なことが多かったです。地方都市ではなおさら、訪日客の気持ちに立ち、迷いや不安を減らせるように、アクセス情報をしっかり発信することが重要だと感じました。」
また、訪日客は市町村や都道府県単位で旅行をするわけではないので、県内だけではなく四国を周遊する際の動き方や高知県から来訪する方なども考えて情報発信をする必要があるなと感じています。
3. 地方の観光資源をどう活かすか?
三好さんと秋山さんは、「地元の人が気づいていない魅力を掘り起こすことが重要」と語りました。
例えば、SNSクリエイターのクリスティーナさんが自身のInstagramで西予市での漁業体験を紹介した際、「日本の田舎で本物の漁に同行できるなんて知らなかった!」と海外からの反響が大きく、発信直後に400件以上のコメントが寄せられました。実際に船に乗り、漁師の仕事を間近で見られる体験は、地元の人にとってはただの日常でも、日本のディープな観光に関心がある訪日客にとって新鮮で貴重なもの。こうしたその土地ならではの暮らしに触れてもらえる体験は心に残ること間違いないですし、海外の方から日々の暮らしに対して良いコメントをいただけることで、地域の人がインバウンドへのハードルが下がり、理解が深まっていくというような流れができてくると思いました。
4. 成功の鍵はリアルな関係性と長期的なビジョン
広域連携を成功させるためには、行政・事業者・地域住民の連携が不可欠です。
- 行政と事業者の連携: 自治体ごとに観光戦略が異なると、効果的なプロモーションが難しくなる。そのため、地域内でビジョンを共有し、一貫性を持った施策を行うことが重要。
- 地域住民との関係づくり: オンラインだけでは伝わらないリアルな交流が、地域の信頼を築く鍵となる。「何度も足を運び、顔を合わせることが、広域連携を成功させるポイント」と三好さん。
- 長期的な視点を持つ: 観光誘客は短期的な成果を求めるのではなく、5年後・10年後を見据えた計画が必要。各自治体のターゲットやブランディングを明確にし、一貫したプロモーションを行うことで、持続可能な観光モデルを構築できる。
■ 参加者の声
- 「若い方が地域の活性化に取り組んでいるのが刺激になった」
- 「観光はすぐに成果が出るものではない。長期的な戦略が大事だと再認識した」
- 「公共交通の情報発信の重要性がよく分かった」
- 「単体のプロジェクトで終わらせない工夫が勉強になった」
■ おわりに
今回のMラボRADIOでは、広域連携によるインバウンド誘客の可能性や、地域ごとの特性を活かした観光戦略について、多くの学びがありました。特に、ペルソナ設定の重要性や、地域プレイヤーとのリアルな関係性の構築が成功の鍵になるという点が印象的でした。
愛媛県南予エリアの取り組みは、他の地域にとっても参考になる部分が多く、今後の動向が注目されます。MATCHAでは引き続き、地方のインバウンド誘客の取り組みをサポートし、情報発信を続けていきます。
📢 次回のMラボRADIO開催情報、過去のMラボRADIOのアーカイブもMATCHAラボで視聴可能です!
https://lab.matcha-jp.com/menus/knsjs6ycbsjjxpqo/announcements
引き続き、皆さまとともに日本各地の魅力を世界へ届けていきたいと思います!
MATCHA週間
インバウンドニュース
メルマガ登録フォーム
インバウンドに取り組む事業者、関心層が5,000人以上購読!
インバウンドに関するニュースを
毎週わかりやすくお届けします。